「また休むのか…」
同僚や部下から3日連続で会社を休むという連絡を受けたとき、こんな思いが頭をよぎったことはありませんか。
もちろん、本当に体調が悪いのかもしれません。

しかし、休むタイミングや理由に不自然さを感じると、「もしかして仮病なのでは?」と疑ってしまうのも無理はないでしょう。
この記事では、会社を3日も仮病で休むのではないかと疑われる社員への対応に悩むあなたのために、その背景にある心理から、パワハラを避けつつ行うべき正しい対処法までを、分かりやすく解説していきます。
もしかして?会社を3日休むのは仮病?そのサインと心理
「またか…」という思いが頭をよぎる、部下や同僚からの突然の欠勤連絡。
特にそれが3日も続くとなると、周りの負担も増え、「本当に体調が悪いのだろうか」と疑念が生まれるのも無理はありません。
しかし、感情的に「仮病だ」と決めつけてしまうのは非常に危険です。
ここではまず、相手の状況を冷静に判断するために、ずる休みをしてしまう人の心理的な背景や、仮病と本当に心身の不調を抱えている場合の見極め方について、客観的な視点から見ていきましょう。
仮病を疑う前に|「ずる休み」をしてしまう人の特徴と心理
つい「ずる休み」という言葉を使いたくなる状況ですが、その行動の裏には、本人なりの理由や心理が隠れている可能性があります。
もちろん、単に仕事への意欲が低いケースもありますが、一括りにはできません。
一般的に、仮病を使ってしまいがちな人には、いくつかの共通した特徴や心理状態が見られることがあります。
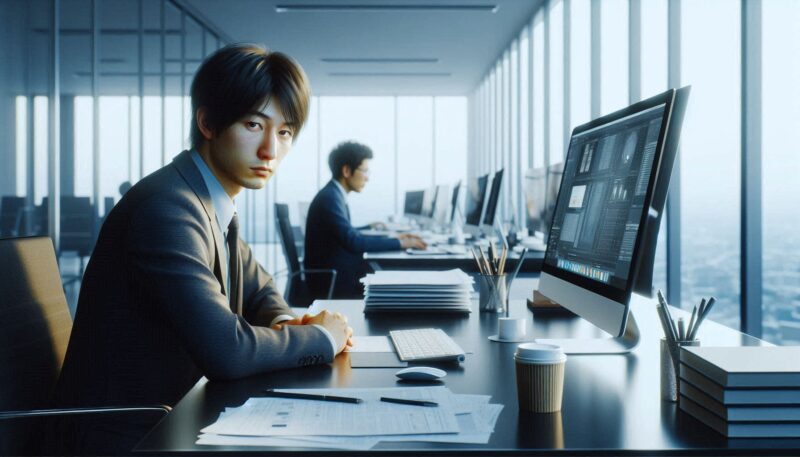
ずる休みをしてしまう人の特徴
- ストレスへの耐性が低い: 仕事のプレッシャーや人間関係のストレスをうまく処理できず、現実から逃避するために休みを選択してしまうことがあります。
- 責任感が希薄: 自分の仕事がチームに与える影響をあまり深く考えておらず、休むことへのハードルが低い傾向があります。
- コミュニケーションが苦手: 悩みや問題を周囲に相談できず、一人で抱え込んだ結果、出社する気力がなくなってしまうケースです。
- 完璧主義: 常に完璧な成果を出さなければならないというプレッシャーから、少しでもうまくいかないことがあると心が折れ、出社できなくなってしまうことがあります。
行動の裏にある心理状態
彼らが仮病という手段を選ぶ背景には、「今の状況からとにかく逃げたい」という強い逃避願望があります。
それは、仕事の大きなプレッシャーであったり、職場の人間関係の悩みであったり、あるいはプライベートの問題かもしれません。
また、周囲からの承認や関心を得たいという気持ちが、体調不良をアピールする行動に繋がっている可能性も考えられます。
これらの特徴や心理を理解することは、相手を一方的に責めるのではなく、問題の根本原因を探る第一歩となります。
会社を3日休む際に使われがちな理由【風邪・体調不良など】
会社を3日連続で休む場合、その理由として使われやすいものには一定の傾向があります。
これらの理由が使われやすいのは、症状の程度を証明しにくく、数日間続くことがあっても不自然に思われにくいからです。
あなたの部下や同僚が使っている理由と照らし合わせてみてください。

よく使われる理由の例
- 風邪や発熱: 最も一般的で、使いやすい理由の一つです。「熱が38度あって…」と言われれば、無理に出社を強いることはできません。数日間、熱が上がったり下がったりすることは珍しくないため、3日程度休む理由としても通用しやすいのです。
- ひどい頭痛や腹痛: 「起き上がれないほどの頭痛がする」「お腹が痛くて動けない」といった理由もよく使われます。これらの症状は他人の目には見えず、本人の申告に頼るしかないため、仮病に利用されやすい側面があります。
- 胃腸炎や食あたり: 嘔吐や下痢といった症状を伴うため、出社が困難であると伝えやすい理由です。感染性を疑わせることで、「他の人にうつすと悪いので」という大義名分も成り立ちます。
- 家族の看病や不幸: 「親が倒れた」「祖母が危篤で…」といった理由は、非常にデリケートな問題であるため、会社側も深く追及しにくいものです。しかし、これを繰り返す場合は、信憑性が疑われる原因にもなります。
これらの理由が伝えられたからといって、即座に仮病と断定することはできません。
しかし、特定の理由が特定の曜日に繰り返されるなど、何らかのパターンが見られる場合は、注意深く様子を見る必要があるかもしれません。
安易な決めつけは危険!仮病と精神的な不調の見極め方
部下や同僚が会社を3日休む際、その背景には精神的な不調が隠れている可能性も十分に考えられます。
「仮病に決まっている」と安易に決めつけて対応してしまうと、本当に助けを必要としている人を見過ごし、状況をさらに悪化させてしまうことになりかねません。
仮病のサインと、精神的な不調のサインには、いくつかの違いが見られることがあります。

仮病が疑われるサイン
- 休むタイミングにパターンがある: 月曜日や連休明け、特定の業務がある日に休むことが多い。
- 連絡時の様子: 電話の声は意外と元気だったり、メールの文面が必要以上に丁寧だったりする。
- SNSの動き: 本人は体調不良で休んでいるはずなのに、SNSでは楽しそうな投稿をしている。
- 復帰後の態度: 休んだことへの罪悪感があまり見られず、ケロッとしている。
精神的な不調が疑われるサイン
- 休む前の変化: 徐々に口数が減る、表情が暗くなる、遅刻やケアレスミスが増えるといった前兆が見られる。
- 連絡の内容: 休みがちになるだけでなく、「眠れない」「食欲がない」といった具体的な心身の不調を訴えることがある。
- 復帰後の様子: 表情が晴れず、集中力を欠いているように見える。周囲とのコミュニケーションを避けるようになる。
- 全般的なパフォーマンスの低下: 以前と比べて、明らかに仕事の質やスピードが落ちている。
もちろん、これらはあくまで一般的な傾向であり、全ての人に当てはまるわけではありません。
大切なのは、「仮病か、それとも本当に不調なのか」を白黒つけることではなく、「何らかのサインを発している」という事実に目を向けることです。
決めつけによる対応は、ハラスメントに繋がるリスクもはらんでいます。
まずは客観的な事実として、本人の様子や行動の変化を冷静に観察することが重要です。
放置がもたらす職場への悪影響とは?チームの士気が下がる前に
特定の誰かが頻繁に3日間も休む状況を、「またか」と思いつつも放置してしまうと、職場全体に深刻な悪影響が及ぶ可能性があります。
それは単に仕事が滞るという問題だけにとどまりません。

業務負担の偏りと増加
最も直接的な影響は、休んだ人の仕事を他のメンバーが肩代わりしなければならないことです。
一時的なことであれば「お互い様」で済みますが、常態化すると特定の社員にばかり業務負荷が集中し、疲弊させてしまいます。
これにより、残業が増えたり、本来の業務に集中できなくなったりと、生産性の低下に直結します。
チームの士気とモチベーションの低下
真面目に出社している社員からすれば、「なぜあの人ばかり休めるのか」「自分が頑張っているのが馬鹿らしい」といった不公平感が募ります。
このような不満は、チーム全体の士気を著しく低下させる原因となります。
職場の連帯感が失われ、協力し合う雰囲気がなくなり、個々がバラバラに仕事をするような、活気のない職場になってしまうでしょう。
職場規律の乱れと不信感の増大
「あの人が許されるなら、自分も」と考える人が現れ、職場全体の規律が緩んでしまう恐れもあります。
ルールを守ることが軽視されるようになると、組織としての統制が取れなくなります。
また、管理職がこの問題を見て見ぬふりをしていると、「上司はきちんとマネジメントしてくれない」という不信感が生まれ、信頼関係が損なわれることにも繋がります。
これらの悪影響が広がる前に、問題を放置せず、適切な対応を取ることが、健全な職場環境を維持するために不可欠なのです。
仮病は会社にバレる?発覚しやすい典型的なケースを紹介
仮病を使って会社を休んでいる本人は「うまくやっている」と思っているかもしれませんが、意外なところから発覚するケースは少なくありません。
もし部下や同僚の休みが仮病ではないかと疑っている場合、以下のような典型的な発覚パターンを知っておくことは、状況を客観的に見る上で参考になるかもしれません。

SNSでの投稿
最も発覚しやすいのが、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)での投稿です。
「体調不良で寝込んでいる」はずの日に、旅行先やイベント会場で楽しんでいる写真や動画をアップしてしまうケースは後を絶ちません。
公開範囲を限定していても、共通の知人などを通じて、会社の誰かの目に触れてしまう可能性は十分にあります。
第三者からの目撃情報
休んでいる日に、外出先で偶然、同僚や取引先の人と遭遇してしまうパターンです。
「昨日、駅前で元気そうに歩いていたよ」といった噂は、あっという間に社内に広まります。
本人は会社の近くには行かないように注意しているかもしれませんが、行動範囲が広ければ広いほど、そのリスクは高まります。
言動の矛盾
復帰した後の会話の中で、辻褄が合わないことを言ってしまうケースです。
例えば、「ずっと寝ていた」と言っていたのに、休んでいた日に放送されていたテレビ番組の内容を詳しく話してしまったり、旅行のお土産をうっかり渡してしまったりするなど、些細な言動の矛盾から疑念が深まることがあります。
同僚や友人からの情報
休んだ理由が嘘であった場合、本人が信頼している同僚や友人にだけ本当のことを話していることがあります。
しかし、その話が何かのきっかけで他の人に伝わり、結果として会社に知られてしまうことも珍しくありません。
これらのケースからも分かるように、嘘をつき通すことは非常に困難です。
仮病が発覚した場合、本人は信用を失うだけでなく、社内での立場が非常に悪くなることを理解する必要があります。
会社を3日休む仮病への対処法|部下・同僚への正しい伝え方
部下や同僚が仮病で会社を3日も休んでいるのではないかという疑念が深まったとき、感情的に問い詰めたり、見て見ぬふりをしたりするのは得策ではありません。
職場の秩序を保ち、本人のためにも、冷静かつ建設的な対応が求められます。
しかし、一歩間違えればパワハラと受け取られかねないデリケートな問題でもあります。
ここでは、それぞれの立場から取るべき具体的なステップと、絶対に守るべき注意点について詳しく解説していきます。
【立場別】仮病が疑われる社員への具体的な対応ステップ
仮病が疑われる社員への対応は、自分の立場が「上司」なのか「同僚」なのかによって、取るべき行動が大きく異なります。
それぞれの役割を理解し、適切なステップを踏むことが、問題をこじらせずに解決へと導く鍵となります。

上司(管理職)として対応する場合
上司には、部下の労務を管理し、職場環境を維持する責任があります。
感情的にならず、以下のステップで冷静に対応しましょう。
- 事実の記録と客観的な状況把握: まずは感情を排し、事実を記録します。「いつ、どのような理由で休んだか」「休む頻度や曜日にパターンはあるか」「休む前の勤務態度はどうだったか」などを客観的に記録しておきましょう。これは、後の面談や、万が一の場合の証拠としても重要になります。
- 1on1でのヒアリング(面談)の実施: 本人と1対1で話す機会を設けます。このとき、「仮病だろう」と決めつけるような詰問は絶対に避けてください。「最近、休みが続いているけど、何か困っていることはない?」「体調で心配なことがあれば聞かせてほしい」など、相手を気遣う姿勢で、オープンな質問を投げかけ、本人が話しやすい雰囲気を作ることが大切です。
- 業務状況の確認と調整: 面談の中で、過重な業務負担や人間関係の悩みなどが明らかになった場合は、その原因を取り除くための具体的なアクションを検討します。業務量の調整や役割分担の見直しなど、会社としてサポートできることを示しましょう。
- 会社の方針とルールの再確認: 話し合いの最後に、無断欠勤や虚偽の申告が続いた場合の就業規則上のルールなどを、冷静に、かつ毅然とした態度で伝えます。これは罰を与えるためではなく、社会人としての責任を再認識してもらうために必要なプロセスです。
同僚として対応する場合
同僚の立場から直接本人を追及するのは、人間関係を悪化させるだけで、良い結果には繋がりません。
やるべきことは、自分の業務と職場環境を守るための行動です。
- 直接の詮索や追及は避ける: 「本当に病気なの?」などと本人に直接問いただすのはやめましょう。噂話を広めることも、職場の雰囲気を悪くするだけです。
- 業務への影響を上司に相談する: 問題は、あなたがその同僚のせいで迷惑を被っていることです。感情的に「あの人が仮病で…」と訴えるのではなく、「〇〇さんが頻繁に休むため、こちらの業務に△△という支障が出ており、負担が増えている状況です」というように、客観的な事実と業務への影響をセットで上司に報告・相談しましょう。
- 本人には体調を気遣う姿勢で: 本人と話す機会があれば、「体調、大丈夫?」と声をかける程度に留めておきましょう。過度に心配したり、逆に冷たい態度を取ったりする必要はありません。あくまでフラットな同僚としての関係を保つことが、自分の精神衛生上も重要です。
立場によって役割は異なりますが、共通して重要なのは「一人で抱え込まず、冷静に、客観的な事実に基づいて行動する」ということです。
これだけは守りたい!パワハラにならないための注意点
仮病が疑われる社員に対応する際、最も注意しなければならないのが「パワーハラスメント(パワハラ)」です。
良かれと思って行った指導が、相手にとってはパワハラと受け取られ、事態をさらに複雑にしてしまう可能性があります。
自分の身を守り、相手を追い詰めないためにも、以下のNG行動は絶対に避けてください。

大勢の前での叱責や注意
他の社員がいる前で、「また休んだのか」「本当に体調が悪いのか」などと問い詰める行為は、相手に屈辱感を与え、典型的なパワハラに該当します。
指導や注意が必要な場合は、必ず個室など、他の人に聞かれない場所で行いましょう。
人格を否定するような発言
「社会人として失格だ」「あなたがいると迷惑だ」といった、相手の人格や存在そのものを否定するような言葉は、指導の範囲を逸脱しています。
注意すべきは、あくまで「頻繁に休む」という行動や事実に対してであり、その人の人格ではありません。
「仮病だろ」と決めつけて詰問する行為
客観的な証拠がないにもかかわらず、「嘘をついているだろう」「本当のことを言え」と一方的に決めつけて相手を追い詰めるのは、非常に危険です。
相手が本当に心身の不調を抱えていた場合、症状を悪化させるだけでなく、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
プライベートへの過度な詮索
休んだ理由について、必要以上にプライベートな事情を根掘り葉掘り聞くことも、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。
「誰とどこに行っていたんだ」といった質問は、業務上の指導とは関係ありません。
退職を強要するような言動
「こんなに休むなら、会社を辞めたらどうか」といった発言は、退職勧奨と受け取られかねません。
解雇には厳格なルールがあり、管理職の一存で決められることではありません。
パワハラにならないための基本は、相手を一人の人間として尊重し、客観的な事実に基づいて、冷静にコミュニケーションを取ることです。
感情的になりそうなときは、一度深呼吸を置き、自分の言動が指導の範囲を超えていないか、常に自問自答する姿勢が求められます。
感情的になりそうなときは、一度深呼吸を置き、自分の言動が指導の範囲を超えていないか、常に自問自答する姿勢が求められます。
パワーハラスメントの定義や企業に求められる対策については、厚生労働省の公式サイト「あかるい職場応援団」で詳しく解説されていますので、より正確な情報を確認することをおすすめします。
会社として診断書の提出を求めることはできる?
「本当に体調不良なら、診断書を出してほしい」と考えるのは、管理する立場として自然なことです。
しかし、診断書の提出を求めることは、常に認められるわけではなく、適切な手順と配慮が必要です。

就業規則の確認が第一
まず確認すべきは、自社の就業規則です。
就業規則の中に、「〇日以上連続して欠勤する場合は、医師の診断書を提出しなければならない」といった規定があるかどうかが、提出を求める際の大きな根拠となります。
もし規定があれば、そのルールに則って提出を求めることができます。
就業規則に規定がない場合
規定がない場合でも、労働者には自己の健康状態を会社に報告する義務(自己保健義務)があると解釈されることがあり、業務命令として提出を求めること自体は可能です。
ただし、この場合は特に慎重な対応が求められます。
本人が提出を拒否した場合に、それを理由に懲戒処分などを行うことは難しい可能性があります。
診断書を求める際の伝え方
診断書の提出を求める際は、高圧的な命令口調ではなく、あくまで本人の健康状態を心配しているという姿勢で伝えることが重要です。
- NGな伝え方: 「仮病を疑っているので、診断書を出してください」
- OKな伝え方: 「3日も休むと、こちらも心配です。もしよろしければ、お医者さんの診断書を提出してもらうことは可能でしょうか。会社としても、あなたの体調を正確に把握して、今後の働き方などを一緒に考えたいと思っています」
このように、相手を気遣う言葉を添え、提出が会社としての配慮であることを伝えることで、相手も受け入れやすくなります。
また、診断書の発行には費用がかかるため、その費用を会社が負担するのかどうかについても、事前に明確にしておくと、よりスムーズでしょう。
診断書の提出は、あくまで本人の健康状態を把握し、適切な労務管理を行うための一つの手段です。
相手を疑うための道具として使うのではなく、建設的な目的のために活用するという意識を持つことが大切です。
注意しても改善しない…段階的な対処法と最終手段
一度や二度の面談、指導を行っても、残念ながら本人の行動が全く改善されないケースもあります。
このような場合、事態を放置するわけにはいきません。
より毅然とした、段階的な対応が必要になります。

ステップ1:口頭での注意から書面での指導へ
最初の面談や指導が口頭で行われた場合、次のステップとして指導内容を書面に残すことを検討します。
「〇月〇日の面談で、頻繁な欠勤が業務に与える影響について話し合いましたが、その後も改善が見られません。改めて、就業規則を遵守し、勤務態度を改めるよう指導します」といった内容の指導書を作成し、本人に交付します。
これにより、会社として正式に問題を指摘し、改善を求めたという記録が残ります。
ステップ2:人事部との連携
現場の上司だけで問題を抱え込むのは限界があります。
状況が改善しない場合は、速やかに人事・労務部門に相談し、連携して対応にあたりましょう。
専門部署が介入することで、より法的な観点や会社全体の方針に基づいた、客観的で適切な対応が可能になります。
ステップ3:就業規則に基づく懲戒処分の検討
度重なる指導にもかかわらず、正当な理由なく欠勤を繰り返すなど、職務怠慢が明らかな場合は、就業規則に定められた懲戒処分を検討する段階に入ります。
懲戒処分には、軽いものから順に、以下のような種類があります。
- 譴責(けんせき)・戒告(かいこく): 始末書を提出させ、将来を戒める処分。
- 減給: 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない、などの制限があります。
- 出勤停止: 一定期間、出勤を禁止する処分。その間の賃金は支払われません。
どの処分を選択するかは、本人の行動の悪質性や、これまでの指導履歴などを総合的に判断して決定されます。
最終手段としての「普通解雇」
懲戒処分を経てもなお改善が見られず、労働契約の継続が困難であると判断される場合には、「普通解雇」という選択肢も視野に入ってきます。
ただし、日本の法律では労働者の権利が強く保護されており、解雇は非常にハードルが高いものです。
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。
仮病を理由に即時解雇、ということはまず認められません。
これまでの指導の記録、本人の改善の意欲の有無、業務への支障の程度など、あらゆる要素を考慮した上で、慎重に判断されるべき最終手段であると理解してください。
根本解決へ!働きやすい職場環境を作るための再発防止策
特定の社員への対処と並行して、あるいはそれ以上に重要なのが、そもそも仮病を使ってまで「会社を休みたい」と思わせないような、働きやすい職場環境を作ることです。
個人の問題として片付けるのではなく、組織全体の問題として捉え、再発防止に取り組む視点が不可欠です。

コミュニケーションの活性化と風通しの良い職場づくり
社員が悩みやストレスを一人で抱え込まないように、日頃からコミュニケーションが取りやすい雰囲気を作ることが大切です。
- 定期的な1on1ミーティング: 上司と部下が1対1で話す機会を定期的に設け、業務の進捗だけでなく、キャリアの悩みや人間関係など、雑談も交えて話せる場を作りましょう。
- 感謝や称賛の言葉を伝える: 些細なことでも「ありがとう」「助かったよ」といったポジティブな言葉をかけ合う文化を醸成することで、社員の承認欲求が満たされ、モチベーションが向上します。
業務量の適正化と公平な評価
「頑張っても報われない」「特定の人にばかり仕事が集中している」といった不満は、仕事への意欲を削ぐ大きな原因です。
- 業務の見える化: 誰がどのような仕事を、どれくらい抱えているのかをチーム全体で共有し、業務負荷が偏らないように調整する仕組みを作りましょう。
- 公平で透明性のある評価制度: 努力や成果が正当に評価され、給与や処遇に反映される仕組みを整えることで、社員の不公平感をなくし、納得感を高めることができます。
休暇を取りやすい雰囲気の醸成
皮肉なことですが、「ずる休み」が起こる背景には、「本当に必要なときに休みが取りにくい」という職場の雰囲気がある場合があります。
有給休暇の取得を奨励したり、体調不良の際には気兼ねなく休めるような「お互い様」の文化を育んだりすることで、社員は追い詰められることなく、心身の健康を維持しやすくなります。
メンタルヘルスサポートの充実
精神的な不調は、誰にでも起こりうることです。
会社として、産業医やカウンセラーに気軽に相談できる窓口を設けたり、メンタルヘルスに関する研修を実施したりすることで、社員が安心して働けるセーフティネットを構築することができます。
これらの取り組みは、一朝一夕で成果が出るものではありません。
しかし、組織全体で粘り強く取り組むことで、社員一人ひとりが健康で、意欲的に働ける職場環境が実現し、結果として「ずる休み」という問題の根本的な解決に繋がっていくのです。
まとめ:会社を3日休む仮病への対応で最も大切なこと
部下や同僚が会社を3日も仮病で休むのではないかと感じたとき、感情的に対応してしまうのは禁物です。
大切なのは、まず「なぜ休むのか」という背景に目を向け、冷静に状況を把握すること。
単なる怠慢と決めつける前に、過度なストレスや精神的な不調といった、目に見えないサインが隠れている可能性も考慮しなくてはなりません。
その上で、対応する際には必ず客観的な事実に基づき、パワハラにならないよう細心の注意を払う必要があります。
個別の対応と同時に、誰もが心身の健康を保ちながら働きやすい職場環境を整えていくという、組織としての視点も不可欠です。
この両輪で取り組むことが、問題の根本的な解決に繋がり、チーム全体の生産性を守る鍵となるのです。




コメント