職場の同僚が立てる、飴を舐める音。
カラカラ、カチカチ…一度気になりだすと、どうしても耳について集中できない。
イライラが募って仕事が手につかないけれど、誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか?
実は、その不快感はあなただけが感じている特別なものではありません。

この記事では、なぜ特定の音に強く不快感を覚えてしまうのか、その原因を心理的な側面や脳の仕組みから分かりやすく解き明かします。
その上で、職場で角を立てずに解決するための具体的な対策を7つ厳選してご紹介します。
もう音に悩まされない、穏やかな毎日を取り戻すための第一歩をここから踏み出しましょう。
- なぜこんなに不快?飴を舐める音にイライラする3つの原因
- 【職場編】飴を舐める音が不快で耐えられない時の対策7選
なぜこんなに不快?飴を舐める音にイライラする3つの原因
静かなオフィスに響く、飴を舐める音。
どうして他の人は平気なのに、自分だけこんなにもイライラしてしまうのでしょうか。
「自分の心が狭いのかな…」と自分を責めてしまう人もいるかもしれません。
しかし、その不快感には、ちゃんとした理由があります。
決してあなたの性格だけの問題ではないのです。
ここでは、飴を舐める音がなぜこれほどまでに不快に感じられるのか、その主な原因を3つの視点から詳しく見ていきましょう。
1. 脳が”エラー”と判断する不規則な音だから
私たちの脳は、次に何が起こるかを予測することで、効率的に情報処理を行っています。
たとえば、雨音や川のせせらぎ、規則正しいリズムを刻む音楽などは、ある程度パターンが予測できるため、心地よい環境音として認識されやすいです。
これらの音は「ホワイトノイズ」のように、むしろ集中力を高める効果があることさえ知られています。
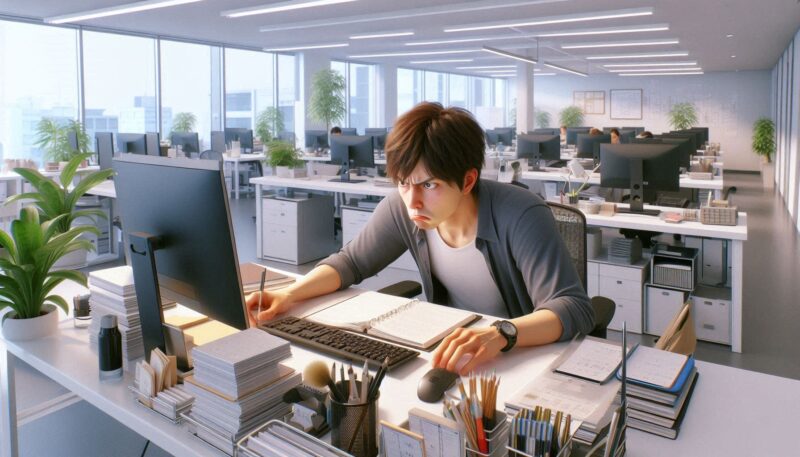
一方で、飴を舐める音は非常に不規則です。
舌で転がす「カラカラ」という音、時折歯で噛む「カチッ」という音、そのタイミングや音量は全く予測できません。
このように予測不可能な音が突然耳に入ってくると、脳はそれを「予期せぬエラー」や「注意すべき異音」として認識します。
そして、集中していた作業から意識を強制的に引き剥がし、「何の音だ?」と注意を向けさせようとします。
この「強制的な注意の切り替え」が何度も繰り返されることで、集中力は著しく削がれ、強いストレスやイライラ感につながるのです。
つまり、飴の音にイライラするのは、あなたの脳が正常に危険を察知しようと働いている証拠とも言えるのです。
2. もしかして病気?特定の音が許せないミソフォニア(音嫌悪症)とは
もし、飴を舐める音だけでなく、人が食事をする時の咀嚼音、鼻をすする音、キーボードのタイピング音など、特定の音に対してだけ強い怒りや憎しみに近い感情を抱くのであれば、それは「ミソフォニア(音嫌悪症)」の症状かもしれません。

ミソフォニアとは?
ミソフォニアは、特定の音(トリガー音)を聞くことによって、ネガティブな感情や身体的な反応が引き起こされる状態を指します。
ギリシャ語で「音の嫌悪」を意味する言葉です。
単なる「うるさいな」と感じるレベルではなく、その音を聞くと怒り、不安、嫌悪感、パニックといった非常に強い感情が湧き上がり、時にはその場から逃げ出したくなったり、攻撃的な衝動に駆られたりすることもあります。
「人の咀嚼音が不快なのは病気ですか?」という疑問を持つ方もいますが、ミソフォニアは比較的新しい概念であり、まだ研究途上の段階ですが、精神医学の世界でも認識されつつある症状です。
決して「わがまま」や「気にしすぎ」で片付けられる問題ではありません。
どんな音が対象になる?
ミソフォニアの引き金となる音は人それぞれですが、一般的には以下のような、人が出す生活音が多いと言われています。
- 口に関連する音: 咀嚼音(クチャクチャ)、飴を舐める音、ガムを噛む音、飲み物を飲む音
- 鼻に関連する音: 鼻をすする音、くしゃみ、いびき
- その他の音: キーボードのタイピング音、ペンのクリック音、貧乏ゆすりの音
もし、これらの特定の音を聞いたときにだけ、自分でもコントロールできないほどの強い不快感や怒りを感じる場合は、ミソフォニアの可能性を考えてみてもよいかもしれません。
3. HSPの気質や聴覚過敏が関係している可能性
病気というほどではないけれど、昔から音に敏感で疲れやすい…という方は、「HSP」や「聴覚過敏」の特性が関係しているかもしれません。

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは?
HSPとは、生まれつき感覚が非常に鋭く、刺激を受けやすい気質を持つ人のことを指します。
これは病気ではなく、あくまで個人の特性です。
HSPの人は、そうでない人が気づかないような些細な音や光、匂いなどを敏感に察知します。
そのため、職場のざわめきや蛍光灯の光、同僚の香水といった様々な情報が一度に流れ込んできて、脳が処理しきれずに疲弊しやすい傾向があります。
特に聴覚が鋭いHSPの人にとって、不意に響く飴の音は、他の人が感じる何倍もの刺激となり、集中を妨げる大きなストレス源となってしまうのです。
聴覚過敏とは?
聴覚過敏は、特定の音や一般的な環境音が、実際よりも大きく聞こえたり、耳に痛みや不快感として響いたりする症状のことです。
耳鳴りやめまいを伴うこともあり、発達障害やうつ病、メニエール病などの症状の一つとして現れることもあります。
聴覚過敏の人は、他の人にとっては「気にならない音」が、まるで耳元で大声を出されているかのように感じられることがあります。
そのため、職場で飴を舐める音が聞こえると、その音だけが頭の中で反響し、他のことが考えられなくなるほどの苦痛を感じることがあるのです。
なぜ平気?飴を舐める音がうるさい人の心理や性格
一方で、なぜ音を立てる側は平気なのでしょうか。
その心理や性格について考えてみることも、あなたのイライラを少しだけ客観的に見る助けになるかもしれません。
大前提として、音を立てている本人には悪気がないケースがほとんどです。

無意識・癖になっている
子どもの頃からの習慣で、音を立てて食べるのが当たり前になっている人は、そもそも自分が音を立てていることに気づいていません。
飴を舐める行為も同様で、完全に無意識の癖になっている可能性が高いです。
特に「おじさんの飴の音がうるさい」と感じるケースでは、昔の日本では今ほど音に対するマナーが厳しくなかった時代背景も関係しているかもしれません。
口寂しさや眠気覚まし
仕事中に口寂しさを紛らわしたり、眠気を覚ましたりするために、無意識に飴を舐めている人もいます。
この場合、本人は仕事に集中するための手段として飴を口にしているので、まさかその音が周囲の迷惑になっているとは夢にも思っていないでしょう。
「飴を舐める人」の性格的傾向
一概には言えませんが、周囲の音を気にしない人は、良く言えば「おおらか」「細かいことを気にしない」、悪く言えば「鈍感」「他者への配慮が足りない」性格である傾向が見られるかもしれません。
自分の世界に没頭しやすく、周囲の状況に意識が向きにくいタイプとも言えます。
しかし、これはあくまで一般的な傾向であり、性格と結びつけて相手を判断するのは早計です。
重要なのは、相手に悪意はなく、ただ「気づいていない」だけだということです。
「クチャラー」と同じ?咀嚼音が不快に感じる心理との共通点
「飴を舐める音」への不快感は、しばしば「クチャラー」と呼ばれる、咀嚼音を立てて食事をする人への嫌悪感と共通する心理が働いています。
「咀嚼音がうるさい人はなぜ平気なの?」という疑問と同じ根っこを持っているのです。
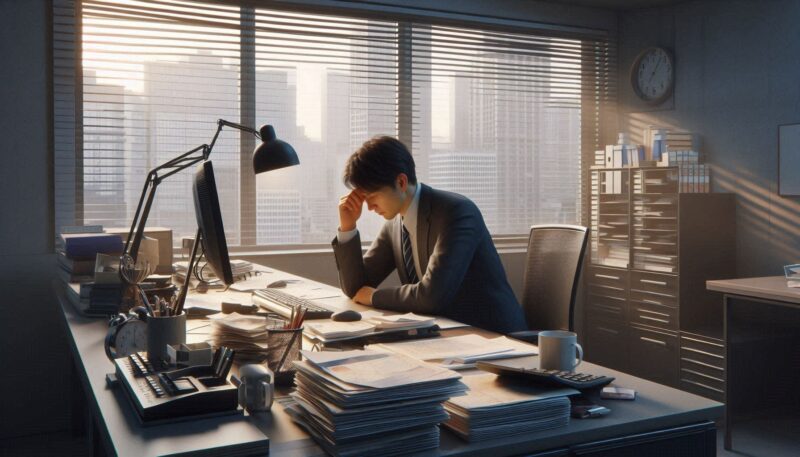
本能的な嫌悪感
口から発せられる湿った音は、本能的に「不潔さ」を連想させ、不快感を抱きやすいと言われています。
また、食事は本来、非常にプライベートな行為です。
そのプライベートな空間から発せられる音を、聞きたくもないのに無理やり聞かされることに対して、自分のテリトリーを侵されたような不快感を覚えるのです。
「じいさんがくちゃくちゃ音を立ててうるさい」と感じるような強い嫌悪感は、こうした本能的な部分に根差している可能性があります。
マナー違反へのいら立ち
食事中の咀嚼音や、仕事中に不必要な音を立てることは、多くの社会でマナー違反とされています。
その「守られるべきルール」が破られている状況を目の当たりにすることで、「なぜこの人は平気でマナー違反ができるんだ?」という怒りや正義感が刺激され、強いストレスを感じるのです。
このように、飴を舐める音への不快感は、単なる音の問題だけでなく、脳の仕組みや個人の特性、さらには本能的な嫌悪感や社会的なマナー意識までが複雑に絡み合って生まれています。
あなたがイライラするのは、決して心が狭いからではないということを、まずは理解してください。
【職場編】飴を舐める音が不快で耐えられない時の対策7選
原因が分かっても、今まさに聞こえてくる不快な音に耐えなければならない状況は変わりません。
特に職場では、人間関係を壊したくないという思いから、我慢し続けてしまう人も多いでしょう。
しかし、ストレスを溜め込み続けるのは心身によくありません。
ここからは、職場の平穏を取り戻すために、今日から試せる具体的な対策を7つのステップに分けてご紹介します。
自分に合った方法から、ぜひ試してみてください。
対策1:【物理的に遮断】ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓を活用する
最も手軽で即効性があるのが、物理的に音をシャットアウトする方法です。
これは、相手に何かを伝える必要がなく、人間関係に波風を立てずに済むという大きなメリットがあります。

ノイズキャンセリングイヤホン
ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンは、周囲の雑音を打ち消す特殊な音波を発生させることで、驚くほどの静寂空間を作り出してくれます。
特に、人の話し声よりも、空調の音やパソコンのファンの音といった持続的な騒音に効果を発揮しますが、飴の「カラカラ」といった突発的な音もある程度軽減してくれます。
職場で使用する際は、「集中したいので、少しイヤホンをさせてください」と周囲に一言断っておくと、コミュニケーションの齟齬を防げるでしょう。
耳栓
イヤホンよりも安価で手軽なのが耳栓です。
最近では、人の話し声は聞こえるのに、不快な高音域の雑音だけをカットしてくれる高性能な耳栓も販売されています。
見た目が目立ちにくいシリコン製のタイプや、自分の耳の形に合わせて成形できるタイプなど種類も豊富なので、自分に合ったものを探してみましょう。
イヤホンと違って音楽を聴いているわけではないので、職場でも使いやすいという利点があります。
対策2:【音で上書き】サウンドマスキングで不快な音をかき消す
不快な音を完全に消すのが難しいなら、別の音で「上書き」してしまうのも有効な方法です。
これをサウンドマスキングと呼びます。
嫌いな音に集中してしまっている意識を、別の心地よい音に向けることで、不快感を和らげる効果が期待できます。

ホワイトノイズや環境音を流す
イヤホンが使える環境であれば、スマートフォンアプリやWebサイトで「ホワイトノイズ(砂嵐のような音)」「ピンクノイズ(雨音に近い音)」、あるいは「カフェの雑音」「波の音」といった環境音を小さな音量で流してみましょう。
一定のリズムを持つこれらの音は、不規則な飴の音をうまく覆い隠し、意識の外に追いやってくれます。
音楽だと歌詞やメロディーに気を取られてしまうという人にもおすすめです。
自分だけのバリアを張るような感覚で、穏やかな音空間を作り出すことができます。
対策3:【自分の心を守る】アンガーマネジメントでストレスと向き合う
音をコントロールできないのであれば、自分の「怒り」の感情をコントロールする方法を身につけるのも一つの手です。
アンガーマネジメントは、怒らないようにするのではなく、怒りと上手に付き合うための心理トレーニングです。
イラっとしたら「6秒」待つ
怒りの感情のピークは、長くて6秒と言われています。
カチッという音がしてイラっとしたら、すぐに反応するのではなく、心の中でゆっくり6秒数えてみましょう。
深く深呼吸をしたり、冷たい水を一杯飲んだりするのも効果的です。
たったこれだけで、衝動的な言動を防ぎ、冷静さを取り戻すことができます。
思考を切り替える練習
「またあの音が始まった…うるさい!」と感じる代わりに、「ああ、あの人は今、眠気と戦っているんだな」「集中するために飴が必要なんだな」と、相手の状況を勝手に想像して、事実と自分の解釈を切り離す練習をしてみましょう。
もちろん、それで音が消えるわけではありませんが、「うるさい人」というネガティブなレッテルを貼るのをやめるだけで、あなたの心は少しだけ楽になるはずです。
音そのものではなく、音に対する自分の「捉え方」を変えることで、ストレスを軽減するアプローチです。
対策4:【環境を変える】可能なら座席の変更を上司に相談する
いろいろ試してもどうしても耐えられない場合は、物理的にその音源から距離を取るのが最も確実な解決策です。
フリーアドレスの職場であれば、さりげなくその席から離れた場所で仕事をするのが簡単です。
座席が固定されている場合は、上司に座席の変更を相談してみましょう。
上司への伝え方のポイント
このとき、正直に「〇〇さんの飴の音がうるさくて仕事に集中できません」と伝えてしまうと、個人への不満と捉えられ、人間関係のトラブルに発展しかねません。
そうではなく、あくまで自分の問題として、ポジティブな理由を添えて相談するのが角を立てないコツです。
<伝え方の例文>
「恐れ入ります、ご相談があるのですが、現在の席が通路に近く、少し落ち着いて業務に取り組めないことがあるため、もし可能でしたら、もう少し静かな環境の席へ移動させていただけないでしょうか。より一層、業務に集中したいと考えております。」
このように伝えれば、上司もあなたの仕事に対する前向きな姿勢と受け取り、協力しやすくなるでしょう。
対策5:【間接的に伝える】職場のマナーとして気づきを促す方法
本人に直接言うのはハードルが高いけれど、何とかしてほしい…という場合には、第三者や全体のルールを通して、間接的に「気づき」を促す方法があります。
上司や総務部に相談する
信頼できる上司や、職場の環境整備を担当している総務部などに、「特定の個人」の問題としてではなく、「職場の労働環境」の問題として相談してみましょう。
「最近、オフィス内で様々な音が気になって集中しにくいと感じる社員がいるようです。快適な職場環境づくりの一環として、音に関するマナーについて、朝礼などで軽くアナウンスしていただくことは可能でしょうか?」といった形で提案してみるのです。
これにより、個人を特定せずに、職場全体のマナー意識を向上させることが期待できます。
対策6:【勇気を出して伝える】角を立てずに「やめてほしい」と伝える言い方
様々な対策を講じても改善が見られない場合、最終的には本人に直接伝えるという選択肢も出てきます。
これは最も勇気がいる方法ですが、最も根本的な解決につながる可能性も秘めています。
伝える上で最も重要なのは、相手を責めるのではなく、自分の気持ちを正直に、かつ丁寧に伝えること(=アイメッセージ)です。
伝える前の準備
- タイミングを選ぶ: 相手が忙しくしている時や機嫌が悪い時は避け、一対一で落ち着いて話せる時間を見つけましょう。
- クッション言葉を使う: 「お忙しいところ申し訳ないのですが」「もし差し支えなければ」といった前置きをすることで、話を切り出しやすくなります。
角が立たない伝え方の例文
NG例:「あなたの飴の音、うるさいのでやめてください!」
→これは相手を一方的に非難しており、反発を招くだけです。
OK例①(自分の特性として伝える)
「〇〇さん、すみません、少しお願いがあるのですが…。実は私が少し音に敏感なところがありまして、飴を召し上がっている時の音が、どうしても気になってしまうことがあるんです。大変申し訳ないのですが、少しだけご配慮いただけると、すごく助かります。」
OK例②(仕事への影響を理由にする)
「〇〇さん、すみません。今、すごく集中しないといけない作業がありまして…。もしよろしければ、その作業が終わるまでだけでも、少し音を控えていただけると大変ありがたいです。」
ポイントは、あくまで「うるさいあなた」が問題なのではなく、「音に敏感な私」の問題として伝えることです。
相手への敬意を払い、丁寧な言葉遣いを心がければ、多くの人は理解し、協力してくれるはずです。
対策7:【最終手段】どうしても改善されない場合は人事部などに相談する
直接伝えても改善されない、あるいは逆上されてしまうなど、状況が悪化してしまった場合は、一人で抱え込まずに会社組織として対応してもらいましょう。
これは最終手段です。
ハラスメントの可能性
特定の個人が発する音が原因で、他の従業員の就業環境が著しく害され、精神的な苦痛によって業務に支障が出ている場合、それは「職場環境配慮義務違反」や、場合によってはハラスメントに該当する可能性があります。
職場におけるハラスメントについては、厚生労働省が運営するポータルサイト「あかるい職場応援団」で詳しく解説されています。
どのような行為がハラスメントにあたるのか、また、相談窓口についての情報も掲載されているため、一度確認してみることをお勧めします。
人事部やコンプライアンス窓口へ
相談する際は、感情的に訴えるのではなく、客観的な事実を整理して伝えることが重要です。
- いつから: 問題の音がいつ頃から気になり始めたか
- 誰が: 音を立てているのは誰か
- どのような音: 具体的にどんな音が、どのくらいの頻度で聞こえるか
- どのような影響: その音によって、あなたの仕事や心身にどのような影響が出ているか
- これまでに行った対策: 自分で試した対策と、その結果
これらの情報を記録としてまとめておくと、相談がスムーズに進みます。
会社には、従業員が安全で健康に働ける環境を整える義務があります。
あなたの悩みを真摯に受け止め、適切な対応(部署の異動や、当事者への指導など)を検討してくれるはずです。
職場の音の問題は、一人で我慢するには限界があります。
まずは自分にできる小さな対策から始めてみて、それでも解決しない場合は、周りの人の力も借りながら、あなたが安心して働ける環境を取り戻していきましょう。
まとめ:「飴を舐める音が不快」もう一人で悩まないための対策
職場で響く、同僚の飴を舐める音。
一度気になると仕事に集中できず、強いストレスを感じてしまいますよね。
しかし、その不快感は決してあなたの心が狭いからではありません。
この記事で解説したように、脳が不規則な音をエラーと判断したり、特定の音に敏感なミソフォニアやHSPといった気質が関係していたりと、その原因は様々です。
大切なのは、一人で我慢し続けないことです。
まずは、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンといった物理的な対策や、自分の心の持ち方を工夫するアンガーマネジメントなど、今日からすぐに始められることから試してみてください。
それでも改善が難しい場合は、上司に相談して環境を変えてもらったり、伝え方を工夫して本人にお願いしたりと、勇気を出して一歩踏み出すことも必要です。
あなたにとって最適な解決策は必ず見つかります。
この記事で紹介した7つの対策を参考に、あなたが穏やかに仕事に集中できる環境を取り戻しましょう。




コメント