「自分より後に入った人が出世した…」。
この事実に直面したとき、言葉にならない悔しさや焦り、そして仕事へのモチベーションが下がってしまうのは、決してあなただけではありません。
その気持ち、よく分かります。
「なぜ自分ではないのか」「評価に納得いかない」と感じるのは、これまで真面目に仕事に取り組んできた証拠です。

この記事では、まず後輩の出世という出来事がなぜ起こるのか、その背景にある様々な理由を冷静に解き明かします。
その上で、下がってしまったモチベーションを取り戻し、再び前を向いて自分のキャリアを築くための具体的な「思考術」を5つのステップでご紹介します。
- 自分より後に入った人が出世する理由とは?考えられる背景を解説
- 自分より後に入った人が出世した時に試したい思考術5選
自分より後に入った人が出世する理由とは?考えられる背景を解説
自分より後に入った人が出世するという現実は、非常に複雑な感情を引き起こします。
しかし、ここで感情的になってしまうと、本質的な原因を見失いかねません。
まずは一歩引いて、なぜそのような状況が生まれたのか、考えられる背景を客観的に探っていくことが大切です。
あなた自身の評価や、会社の方針、そして出世した後輩の特徴など、様々な角度から見ていくことで、次に取るべき行動が明確になります。
後から入ってきた人が優秀で「仕事できる」と評価される特徴
悔しい気持ちは一旦横に置いて、まずは出世した後輩を冷静に観察してみましょう。
もしかしたら、あなたが見過ごしていた、あるいは今の組織で高く評価される「仕事ができる」特徴を持っているのかもしれません。
後から入ってきた人が優秀だと評価される場合、いくつかの共通点が見られることがあります。

圧倒的な学習意欲と吸収力
新しく組織に入ってきた人は、あらゆることをスポンジのように吸収しようとします。
業界の知識、社内のルール、人間関係など、学ぶべきことが山積みだからです。
この高い学習意欲と、新しい情報を素早く自分のものにする吸収力は、成長スピードに直結します。
ベテランになると、つい自分の経験則に頼りがちになりますが、彼らは常に最新の情報をインプットし、それをすぐに業務に活かそうとします。
その結果、短期間で目覚ましい成果を上げることもあるのです。
物怖じしないコミュニケーション能力
経験が浅いことを逆手にとって、彼らは物怖じせずに様々な部署のキーパーソンに質問したり、協力を仰いだりすることができます。
こちらが「今さら聞けない」と感じるような初歩的なことでも、臆することなく確認し、着実に業務の精度を高めていきます。
また、飲み会などの社内イベントにも積極的に参加し、部署を超えた人間関係を構築する能力に長けている場合もあります。
このようなコミュニケーション能力は、円滑に仕事を進める上で非常に重要なスキルとして評価されます。
デジタルツールや新しい手法への順応性
若い世代は、新しいデジタルツールやアプリケーションに対する抵抗感が少なく、むしろ積極的に活用しようとします。
業務効率化ツールや新しいプロジェクト管理手法などをいち早く取り入れ、チーム全体の生産性を向上させるきっかけを作ることもあります。
これまでのやり方に固執せず、常に新しい手法を試そうとする柔軟な姿勢は、変化の激しい現代のビジネス環境において、高く評価される傾向にあります。
既存の枠にとらわれない柔軟な発想力
社歴が長いと、無意識のうちに「こうあるべきだ」という固定観念に縛られてしまうことがあります。
一方で、後から入ってきた人は、まだ会社の常識に染まっていないため、既存の枠にとらわれない新鮮な視点や柔軟な発想で課題解決の糸口を見つけることがあります。
「なぜこの業務は必要なのか?」という根本的な問いを投げかけ、業務プロセスの改善に繋がるような大胆な提案ができるのも、彼らの強みと言えるでしょう。
あなたの「当たり前」は古い?時代と共に変化する会社の評価基準
長年同じ会社に勤めていると、自分の中での「仕事の常識」や「評価されるべき働き方」が凝り固まってしまうことがあります。
しかし、会社の置かれている状況や経営方針の変化に伴い、人事評価の基準も時代と共に変化しています。
かつて評価されていた働き方が、今では必ずしも評価されるとは限らないのです。

かつての「頑張り」が評価されにくい時代へ
以前は、長時間労働や休日出勤も「熱意がある」「頑張っている」と評価される風潮があったかもしれません。
しかし、働き方改革が進む現代では、いかに効率的に、そして短い時間で成果を出すかが重視されるようになっています。
だらだらと残業するよりも、定時で仕事を終え、プライベートの時間で自己投資に励む人材の方が、将来性が高いと判断されることもあります。
あなたの「当たり前」の頑張りが、今の会社の評価基準とズレてしまっている可能性はないでしょうか。
プロセスよりも結果を重視する傾向
真面目にコツコツと努力する姿勢は、もちろん尊いものです。
しかし、ビジネスの世界では、最終的にどのような結果を出したかが最も重要な評価ポイントとなります。
どれだけ素晴らしいプロセスを踏んでいても、それが売上や利益といった具体的な成果に結びつかなければ、評価されにくいのが現実です。
出世した後輩は、もしかしたらプロセスは荒削りでも、会社が求める結果を出すことに長けていたのかもしれません。
チームへの貢献度の測り方の変化
個人の目標達成だけでなく、チーム全体の成果にどれだけ貢献できたかという視点も、近年ますます重要になっています。
例えば、自分が持っている知識やスキルを積極的に他のメンバーに共有したり、チームの雰囲気を良くするための働きかけをしたりといった行動です。
自分の仕事だけを黙々とこなすだけでなく、リーダーシップを発揮してチームをまとめたり、他のメンバーをサポートしたりする能力が、管理職への昇進において高く評価されることがあります。
意外な盲点?後から入ってきた人を優遇する会社の評価制度や方針
個人の能力とは別に、会社側の方針や評価制度そのものが、後から入ってきた人に有利に働くケースも考えられます。
これは、あなた個人の努力ではどうにもならない側面もあり、冷静に会社の状況を把握することが重要になります。
人事評価に納得いかないと感じる背景には、このような組織的な要因が隠れているかもしれません。

組織の若返りを図るための抜擢人事
会社が将来の成長を見据え、組織の新陳代謝を促すために、あえて若手を重要なポジションに抜擢することがあります。
これは、新しい視点や活気を組織に取り込むことを目的とした、戦略的な人事異動の一環です。
長期的な視点に立った経営判断であるため、短期的な実績や経験年数だけでは測れない要素が考慮されている可能性があります。
特定のスキルを持つ人材を高く評価する方針
会社が新規事業に乗り出したり、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進したりする場合、その分野で専門的なスキルを持つ人材が急に高く評価されることがあります。
例えば、デジタルマーケティングやデータ分析、AIに関する知識などです。
後から入ってきた人が、たまたま会社が今まさに求めている特定の専門スキルを持っていたために、スピード出世を果たしたというケースも考えられます。
上層部との関係性(社内政治やえこひいきの可能性)
考えたくはないことですが、上司や役員との個人的な関係性が昇進に影響を与える、いわゆる「社内政治」や「えこひいき」が存在する可能性もゼロではありません。
特定の上司に気に入られている、あるいは社内の有力者と繋がりがあるといったことが、実力以上の評価に繋がっているケースです。
もしこのような状況が明らかであるならば、個人の努力だけでは覆すのが難しい壁があるのかもしれません。
年功序列はもう終わり?成果主義への移行で評価が変わった可能性
日本の多くの企業で長らく採用されてきた「年功序列制度」は、勤続年数や年齢に応じて役職や給与が上がっていく仕組みです。
しかし、近年ではグローバルな競争の激化などを背景に、年齢や経験に関わらず、個人の成果や実績に基づいて評価を行う「成果主義」を導入する企業が増えています。
この大きな変化が、あなたと後輩の評価の違いを生んだのかもしれません。

成果主義とは何か?
成果主義とは、文字通り「成果」を最も重要な評価基準とする考え方です。
ここで言う成果とは、売上目標の達成率、新規顧客の獲得数、コスト削減額など、数値で客観的に示すことができる実績を指す場合が多くなります。
この制度のもとでは、入社1年目の社員であっても、ベテラン社員を上回る成果を出せば、高い評価と報酬を得ることが可能です。
成果が可視化されやすい職種での逆転現象
特に営業職やマーケティング職、エンジニア職など、個人の成果が数字として明確に現れやすい職種では、成果主義が導入されると、ベテランと若手の立場が逆転する現象が起こりやすくなります。
後から入ってきた人が、新しい手法やツールを駆使して驚異的な成果を上げた場合、経験年数に関わらず、一気に出世の階段を駆け上がることがあります。
年齢や経験年数以外の評価軸の存在
成果主義の導入は、評価の軸が多様化したことを意味します。
これまでは経験年数が重視されていたかもしれませんが、今後は「問題解決能力」「リーダーシップ」「新しいことへのチャレンジ精神」といった、年齢とは直接関係のない能力が評価の対象になっている可能性があります。
出世した後輩は、こうした新しい評価軸において、あなたよりも高い評価を得たのかもしれません。
劣等感や焦りの原因は自分の中に?キャリアプランの課題
後輩の出世という外部の出来事だけでなく、自分自身の内面にも、劣等感や焦りを生む原因が隠れているかもしれません。
この機会に、自分自身のキャリアへの向き合い方を一度振り返ってみることも重要です。
もしかしたら、今回の出来事は、あなた自身の課題に気づくためのきっかけになるかもしれません。

スキルアップを怠っていなかったか?
日々の業務に追われる中で、新しい知識を学んだり、スキルを磨いたりすることを後回しにしていませんでしたか?
「今のままで大丈夫だろう」という油断が、知らず知らずのうちにあなたの成長を止めてしまっていた可能性があります。
業界のトレンドは常に変化しており、継続的なスキルアップは、自身の市場価値を維持・向上させるために不可欠です。
後輩が業務時間外に資格取得の勉強をしたり、セミナーに参加したりしていた一方で、自分はどうだったかを冷静に振り返ってみましょう。
自身のキャリアプランを明確に描けていたか?
あなたは、この会社で将来的にどのようなポジションに就き、どのような仕事をしたいのか、具体的なキャリアプランを描けていましたか?
明確な目標がないまま、ただ目の前の仕事をこなしているだけでは、上司に昇進への意欲をアピールすることは難しいでしょう。
一方で、出世した後輩は、入社当初から明確な目標設定を行い、その達成のために何をすべきかを逆算して行動していたのかもしれません。
キャリアプランの有無が、上司からの評価や期待値に差をつけた可能性も考えられます。
会社への貢献をアピールできていたか?
どれだけ会社に貢献していても、それが上司や人事部に伝わっていなければ、正当な評価には繋がりません。
目標設定の面談や日々の報告の中で、自分の成果や貢献を具体的に、そして客観的な事実に基づいてアピールすることは非常に重要です。
「言わなくても分かってくれるだろう」という受け身の姿勢では、損をしてしまうこともあります。
控えめな姿勢が美徳とされる風潮もありますが、ビジネスにおいては、適切な自己評価とアピール能力も評価されるスキルの一つなのです。
自分より後に入った人が出世した時に試したい思考術5選
自分より後に入った人が出世した理由や背景について、様々な角度から考えてきました。
その上で、ここからは下がってしまったモチベーションを回復させ、この状況を乗り越えるための具体的な「思考術」を5つのステップでご紹介します。
感情に流されるのではなく、これを自分のキャリアを見つめ直す良い機会と捉え、次の一歩を踏み出していきましょう。
①感情の整理|「悔しい」という気持ちを客観的に受け止める
最初にすべきことは、自分の中に渦巻くネガティブな感情から目をそらさず、ありのままに受け止めることです。
「悔しい」「むかつく」「なぜだ」といった感情は、決して悪いものではありません。
それは、あなたがこれまで仕事に真剣に向き合ってきた証拠であり、高いプライドを持っているからこそ生まれる自然な反応です。

ネガティブな感情を否定しないことの重要性
「後輩の出世を喜べないなんて、自分は心が狭い人間だ」などと、自分を責める必要は一切ありません。
無理にポジティブになろうとしたり、感情に蓋をしたりすると、かえってストレスが溜まり、仕事への意欲をさらに失ってしまう可能性があります。
まずは、「自分は今、悔しいと感じているんだな」と、自分の感情を客観的に認めてあげることが、心を落ち着かせるための第一歩です。
なぜ「悔しい」のか?感情を細分化してみる
一言で「悔しい」と言っても、その中身は人それぞれです。
なぜ、あなたは悔しいのでしょうか?
- 自分の能力が正当に評価されなかったことへの不満
- 後輩に追い抜かれることへのプライドの傷つき
- 将来のキャリアへの漠然とした不安
- 年下上司とどう接したらいいか分からない戸惑い
このように、感情を具体的に言葉にして細分化してみると、自分が何に一番引っかかっているのかが見えてきます。
原因が明確になることで、漠然としたモヤモヤが晴れ、冷静に対処法を考えられるようになります。
感情を書き出して客観視するワーク
頭の中だけで考えていると、同じことをぐるぐると考えてしまいがちです。
そんな時は、ノートやパソコンのメモ帳などに、今感じていることを正直に全て書き出してみましょう。
誰に見せるわけでもないので、どんな汚い言葉を使っても構いません。
「〇〇(後輩の名前)が出世してむかつく!」「上司の評価は納得いかない!」など、感情をそのまま吐き出すのです。
書き出した文章を少し時間をおいてから読み返してみると、不思議と自分の状況を客観的に見つめることができ、気持ちが整理されていくのを感じるはずです。
②自己分析|自分の市場価値と今後のキャリアプランを再設計する
感情の整理が少しできたら、次は視点を「自分自身」に向けてみましょう。
今回の出来事をきっかけに、これまでの自分の働き方やキャリアを客観的に見つめ直し、今後のプランを再設計する絶好の機会です。
他者との比較ではなく、自分自身の価値を再確認し、未来を描いていきましょう。

これまでの経験・スキルの棚卸し
まずは、これまであなたが仕事を通じて得てきた経験やスキルを、具体的に書き出してみましょう。
- 担当してきたプロジェクトや業務内容
- 達成した成果(具体的な数字で示せるものが望ましい)
- 習得した専門知識や技術
- 取得した資格
- マネジメント経験や後輩指導の経験
どんな些細なことでも構いません。
自分のキャリアを可視化することで、これまで気づかなかった自分の強みや、会社に貢献してきた実績を再認識することができます。
これは、失いかけた自信を取り戻す上で非常に重要な作業です。
自分の強みと弱みを客観的に把握する
スキルの棚卸しができたら、それらをもとに自分の「強み」と「弱み」を分析します。
強みは、今後さらに伸ばしていくべきあなたの武器になります。
弱みは、これから改善すべき課題です。
この時、自分一人の視点だけでなく、信頼できる同僚や上司にフィードバックを求めてみるのも有効です。
360度評価のように、他者からの客観的な視点を取り入れることで、自分では気づかなかった強みや、改善すべき点を明確にすることができます。
また、厚生労働省が提供する職業情報提供サイト「job tag」などを活用して、客観的な自己分析ツールを試してみるのも一つの方法です。
様々な職業情報に触れながら、自身の興味や価値観、スキルを再確認することは、具体的なキャリアプランを立てる上で大いに役立ちます。
今の会社で目指す道、あるいは転職という選択肢
自己分析を通じて自分の現在地が明確になったら、今後のキャリアプランを具体的に考えていきます。
選択肢は一つではありません。
- 今の会社で昇進を目指す:
もし、今の会社にまだ魅力や成長の可能性を感じるのであれば、今回明らかになった課題を克服し、改めて昇進を目指す道があります。上司との面談でキャリアプランを伝え、必要なスキルアップに励むことになるでしょう。 - 専門性を高めてスペシャリストを目指す:
管理職になることだけがキャリアパスではありません。現場の第一線で、誰にも負けない専門性を武器に活躍する「スペシャリスト」という道もあります。 - 転職して環境を変える:
会社の評価制度や将来性に疑問を感じるのであれば、転職も有力な選択肢です。あなたの経験やスキルを、もっと高く評価してくれる会社は他にあるかもしれません。
どの道を選ぶにせよ、大切なのは自分自身で主体的にキャリアを選択するという意識を持つことです。
③他者との比較からの脱却|先輩より先に出世した後輩から学べること
「後輩に追い抜かれる」という考え方そのものが、あなたを苦しめている原因かもしれません。
キャリアはマラソンのようなもので、一時的に前後することはあっても、最終的なゴールは人それぞれです。
他者との比較にエネルギーを費やすのではなく、その状況から何を学べるかに視点を切り替えてみましょう。

「追い抜かれる」という視点を捨てる
そもそも、会社内での出世レースは、人生のほんの一部でしかありません。
「先輩より先に出世する」という事実は、あくまで会社という組織内での出来事です。
その土俵から一度降りて、「自分は自分、他人は他人」と割り切ることで、心の負担は軽くなります。
出世したことで、後輩はあなたにはないプレッシャーや責任を負うことになります。
それぞれの立場で、それぞれの課題があるのです。
出世した「年下上司」の良い点を冷静に分析する
感情的なわだかまりを乗り越え、新しい上司となった後輩の良い点を冷静に分析してみましょう。
彼(彼女)の仕事の進め方、コミュニケーションの取り方、プレゼンテーションの仕方など、客観的に見て「優れている」と感じる部分が必ずあるはずです。
妬みや劣等感といったフィルターを外して観察することで、自分の成長に繋がるヒントが見つかるかもしれません。
新しい上司との接し方に悩む前に、まずは相手を理解しようと努める姿勢が、良好な人間関係を築く第一歩となります。
協力関係を築くことで得られるメリット
年下上司の下で働くことは、プライドが傷つくかもしれません。
しかし、ここで反発したり非協力的な態度を取ったりすれば、あなたの評価はますます下がってしまうでしょう。
むしろ、あなたの豊富な経験と知識で、新しい上司をサポートする姿勢を見せるのです。
「あなたの経験が頼りです」と上司に思わせることができれば、あなたはチームにとって不可欠な存在となり、新たな信頼関係が生まれます。
協力関係を築くことは、結果的にあなた自身の仕事のしやすさや、社内でのポジション確保にも繋がる賢明な選択と言えるでしょう。
④具体的な行動|スキルアップで自信を取り戻し、評価を変える
思考を整理し、マインドセットを変えたら、次はいよいよ具体的な行動に移す段階です。
失った自信を取り戻し、周囲の評価を覆すためには、目に見える形で自分自身を成長させることが最も効果的です。
小さな一歩からでも構いません。
今日から始められるスキルアップに挑戦してみましょう。

不足しているスキルを明確にする
自己分析のステップで見えた自分の「弱み」や、出世した後輩が持っている「強み」を参考に、今あなたに不足しているスキルは何かを具体的に洗い出します。
- マネジメント能力
- リーダーシップ
- 特定の専門知識(例:語学、プログラミング)
- プレゼンテーション能力
- コミュニケーション能力
課題が明確になれば、何を学ぶべきかという道筋が見えてきます。
資格取得や研修参加など、具体的な目標設定
学ぶべきスキルが決まったら、それを達成するための具体的な目標設定を行います。
漠然と「頑張る」のではなく、「3ヶ月後までに〇〇の資格を取得する」「今月中に〇〇に関する本を3冊読む」といった、期限と具体的な行動をセットにした目標を立てることが重要です。
会社で推奨されている研修プログラムに参加したり、外部のセミナーを探してみるのも良いでしょう。
目標に向かって努力するプロセスそのものが、あなたのモチベーションを再び高めてくれます。
小さな成功体験を積み重ね、モチベーションを維持する
いきなり大きな目標を立てると、挫折しやすくなります。
まずは、「毎日30分、勉強する」「週に一度、新しい業務改善案を考える」といった、少し頑張れば達成できるレベルの小さな目標から始めましょう。
そして、それを達成できたら自分を褒めてあげてください。
このような小さな成功体験を積み重ねていくことで、「自分もやればできる」という自己効力感が高まり、それが自信となって仕事への姿勢にも良い影響を与えます。
⑤環境の見直し|「後輩に出世されたから辞めたい」と考える前に
悔しさや失望から、「こんな会社、辞めたい」と衝動的に考えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、感情的な勢いだけで退職を決断するのは非常に危険です。
今の環境で本当にやるべきことは全てやったのか、そして会社の評価は本当に不当なのかを、もう一度冷静に見極める必要があります。
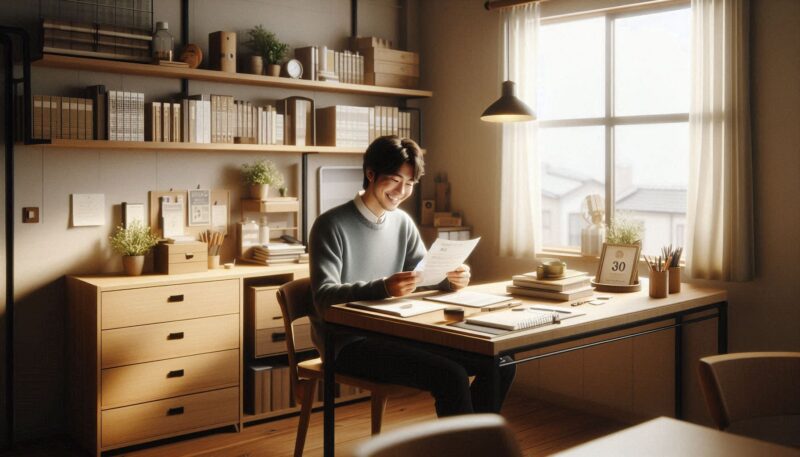
人事評価に納得いかない場合の適切な行動とは?
もし、客観的に見て人事評価に納得がいかない点があるのであれば、感情的に不満をぶつけるのではなく、冷静に上司に説明を求めることが重要です。
その際は、「なぜ〇〇さんが出世して、私ではないのですか?」といった他者との比較ではなく、「私が次のステップに進むためには、どのようなスキルや実績が不足しているのでしょうか?」という形で、あくまで自分自身の課題として質問する姿勢が大切です。
具体的なフィードバックを求めることで、会社があなたに何を期待しているのかが明確になり、今後の行動計画も立てやすくなります。
会社の将来性や自身の成長可能性を再評価する
一度、自分の感情は脇に置いて、純粋に会社の事業内容や将来性、そしてこの環境で自分自身が今後も成長できる可能性があるのかを再評価してみましょう。
- 会社の業績は安定しているか、成長しているか?
- 自分がやりたい仕事に挑戦できる環境か?
- 尊敬できる上司や同僚はいるか?
これらの問いに対して、ポジティブな答えが見つかるのであれば、まだこの会社で頑張る価値は十分にあると言えるでしょう。
衝動的な退職のリスクを理解する
勢いで退職してしまった場合、次の職場がすぐに見つかるとは限りませんし、新しい環境が必ずしも良いとは限りません。
特に、ネガティブな理由での転職は、面接でも見抜かれやすく、不利に働くことがあります。
「後輩に出世されたから辞めたい」という気持ちは、あくまできっかけの一つとして捉え、まずはこの記事で紹介した思考術を実践し、自己分析やスキルアップに取り組んでみてください。
それでもなお、この会社では自分の未来が描けないと判断した時に、初めて転職という選択肢を本格的に検討するのが賢明な判断と言えるでしょう。
まとめ:自分より後に入った人が出世した時に考えたいこと
自分より後に入った人が出世したという事実は、誰にとっても大きなショックであり、仕事へのモチベーションを維持するのが難しくなるものです。
この記事では、まずその後輩が評価された理由や、会社の評価基準の変化といった、考えられる様々な背景を客観的に分析しました。
その上で、下がってしまったモチベーションを取り戻すための具体的な思考術として、①悔しい感情を受け止める、②自己分析でキャリアを再設計する、③他者との比較から抜け出す、④スキルアップで自信を取り戻す、⑤環境を冷静に見直す、という5つのステップを紹介しました。
この出来事は、決してあなたのキャリアの終わりではありません。
むしろ、自分自身の市場価値を見つめ直し、今後の働き方を主体的にデザインしていくための絶好の機会です。
感情に流されることなく、この記事で紹介した思考術を実践し、あなたらしいキャリアを築くための一歩を踏み出してください。




コメント